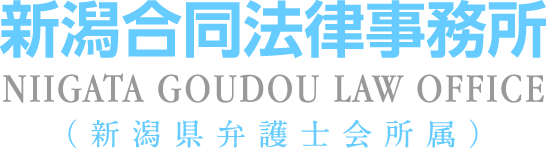2019年1月8日
クラシカがある暮らし
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、皆さんはクラシック音楽をお聴きになるでしょうか?クラシックは、つまらない、堅苦しいというイメージがあるかもしれません。
とはいえ、CMやBGMでクラシック音楽が使用されることは少なくなく、誰にでも、聴き覚えがあるクラシックの曲があるのではないでしょうか。
また、ロック、ジャズ、R&B、あのデスメタルでさえも、元の元をたどっていけばクラシック音楽の影響を受けながら発展してきたという歴史があり、クラシックはまさに現代の音楽の源流といえるでしょう。
私がクラシック音楽を聴くようになったのは20代半ばのころで、きっかけはサッカーでした。もともとサッカーが好きで、サッカーを観ているうちに、イタリアの応援歌でオペラ『アイーダ』(ベルディ)の「凱旋行進曲」が使われていたことから、クラシック音楽に興味をもつようになりました。映画「ショーシャンクの空に」の中で、服役中の主人公がオペラ『フィガロの結婚』(モーツアルト)のレコードをかける場面も印象的です。
今では、例えば、気合を入れるときは「ワルキューレの騎行」(ワーグナー)、交響曲第5番「運命」(ベートーベン)、明るい気分になりたいときは「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」(モーツアルト)、「シバの女王の入城」(ヘンデル)、気持ちを落ち着かせるときには「カノン」(パッヘルベル)、「前奏曲第7番」(ショパン)、「行け、わが想いよ、黄金の翼にのって」(ベルディ)などを聴いています。ほかでは、J・シュトラウス2世やチャイコフスキーも聴きやすく美しいメロディーが多い作曲家です。
さて、一口にクラシックといっても、年代による区分、交響曲、オペラなど演奏形式による区分、楽器ごとの曲、また、作曲家ごと、指揮者ごと、演奏家ごとにも分類することができ、ジャンルが広く、すべてを網羅することは到底不可能です。なので、とりあえず、定番や有名な曲を聴くことが多いです。
たまにコンサートにも行きますが、クラシックコンサートの魅力は、何と言ってもマイクやアンプを通さない生の音を味わえるということです。座席は、ホールの後方がおすすめです。あまり前すぎる席だと音が頭上をすぐ通過して行ってしまうからです。
コンサートでの鑑賞ルールというものは、思われているほど面倒なものではありません。ラフ過ぎる服装は避けたほうがよいということと、演奏中は私語などをせず静かに聞くことと、拍手をする、止めるタイミングくらいです。拍手のタイミングは周りに合わせていれば問題ありません。
CDで聴くにしてもコンサートで聴くにしても、クラシックだからといって固く構えず、楽な気持ちで、文字どおり「音」を「楽」しむことがコツのように思います。
お正月は、気分を新たにクラシック音楽を聴いてみては如何でしょうか。
弁護士 小淵真史(ほなみ第125号)
「子連れOKですか?」
「勾留理由開示」について