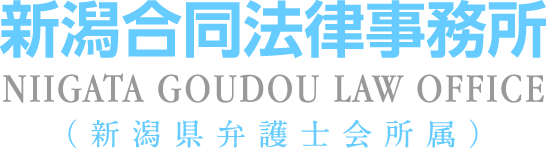2022年1月20日
声を上げるということ
子どものいじめ自殺が後を絶ちません。いじめられているとの声を上げられないまま、命を落としてしまう子どもも少なくありません。
わが国の学校教育は、人権を「思いやり」として教える傾向があります。文科省のホームページの人権教育についての記述によれば、人権について、「児童生徒にもわかりやすい言葉で表現するならば、[自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること]であるということができる」と説明しています。そして「思いやり」の観点から、いじめはいけないことだと指導しています。
人を思いやり、大切さを認めることは、教育上重要なことだと思います。しかし「思いやり」の精神は人権の一側面にすぎないことを忘れてはいけません。人権の重要な意義と機能は、第一に、人間が生まれながらにして誰でも有する人間が人間らしく生きるための権利であること、第二に、それが侵害されたら侵害行為を排除するように求める権利があることのはずです。
また、「思いやり」ばかりを強調することは、人権保障は、市民一人ひとりの意識や行動の問題であるという見方につながり、本来人権を保障すべき責任を負っている国家(行政)の責任を影に隠してしまうおそれがあると思います。
「思いやり」でいじめをやめるべきだと指導することは正しいことでしょう。しかし、いじめられている生徒がもっと声を上げやすくするにはどうしたらよいか、という観点があり重要になっていると思います。「思いやり」に偏重した人権教育は見直されるべきではないでしょうか。
いじめの問題にかかわらず、わが国では「声を上げる」文化が弱いと言われます。私も、日本人の「思いやり」「和」「協調」という美徳は素敵だと思いますが、そのことが、大事な時でさえ「声を上げる」ことができないことにつながっているとすれば問題です。
今年がみなさんにとって人間らしさが守られる年となることをお祈りするとともに、みなさんが「声を上げる」ことが必要になったとき、弁護士としてそのお手伝いができればと考えています。
弁護士 近 藤 明 彦
(事務所誌「ほなみ」第131号掲載)
「ちむ」にはふたつの意味がある
わすれこき