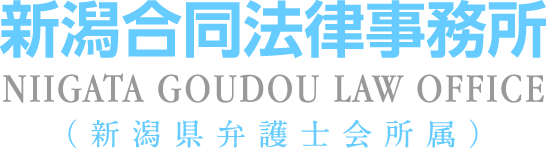2019年1月7日
「勾留理由開示」について
憲法34条には「何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない」と規定されており、この規定に基づき、刑事訴訟法は「勾留理由開示制度」を定めています。裁判官が検察官からの勾留請求に対して「犯罪の嫌疑があり、勾留の理由(住居不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれ)と勾留の必要性がある」と判断したわけですので、その理由を公開の法廷で明らかにしてもらうための手続といえるでしょう。
しかし、勾留理由開示の手続きで裁判官が行う「理由の開示」は「一件記録によれば、刑事訴訟法●号に該当する」といった抽象的な理由が述べられることも多く、実際の事件に沿った具体的な勾留の理由が開示されることはほとんどありません。なお、このような裁判官からの理由の開示に対し、弁護人としても、より詳しい勾留理由の説明を求めることになるわけですが、これに対して裁判官は「捜査中」であることを理由にして回答しないこともしばしばです。このような運用は本来の勾留理由開示制度の趣旨に反しており、「人質司法」と言われる現在の刑事司法の問題点ともいえます。
そのためなのか、実際の刑事弁護の中で勾留理由開示請求を行うことは実は多くはありません。私が弁護人として勾留理由開示請求を行ったケースでは、身柄拘束が不要であることを改めて裁判所に検討させ勾留延長を阻止するために行ったものもありますが、接見禁止決定がなされている事案で精神的な支援のため、家族や支援者と公開の法廷で会える機会を持つために行ったものなどがあります。
1月8日には社会的に注目される「勾留理由開示手続」が予定されています。当該事件の裁判官はどのように理由を開示するのでしょうか。他の多くの事件と同様に抽象的な理由で終わるとすれば日本の刑事司法のあり方が問題視されることは必至です。他方で、特別扱いと言わんばかりに具体的に理由を開示するとなれば、それはそれで違和感を感じざるを得ません。
弁護士 二宮淳悟
著者:二宮 淳悟
![]()
2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長 ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長
クラシカがある暮らし
高校野球の球数制限について