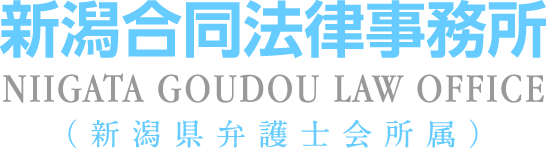2011年1月13日
百人一首の世界を楽しむ
百人一首の「かるた」競技は、正月の風物に欠かせないものです。
瀬をはやみ 岩にせかるる滝川の 割れても末に あはむとぞ思ふ (崇徳院)
この歌は崇徳院の有名な和歌ですが、商家の若旦那が神社にお参りをした際に茶屋で出会った娘に一目惚れして、「瀬をはやみ~」と言いながら、その娘を捜す古典落語の「崇徳院」の話にも出てくる歌です。
このほか、「ちはやぶる」という落語も、在原業平の「ちはやふる神代もきかず龍田川からくれないに水くくるとは」の歌を題材にした話です。「先生」の異名をもつ岩田の隠居が八五郎という無学の者に、この歌の解釈を聞かれ、竜田川という大関が千早という女郎に振られる(ちはやふる)という解釈をして、物知り顔をするという上方落語です。
ところで、百人一首の歌の中には遣唐使として中国に渡った歌人の歌もあります。
天の原ふりさけ見れば春日なる 三笠の山に出し月かも (阿部仲麻呂)
この歌は、遣唐使として唐に渡った阿部仲麻呂が、長安(現在の西安)の都の空に昇る月も三笠山に出る月も同じだろうなあと望郷の念を歌ったよく知られた歌です。
遣唐使が伝えた中国の文化は古代の日本の文化に大きな影響を与え、熱心な仏教徒であった天皇家によって仏教が普及し、西域の美術品や工芸品が伝えられています。
阿部仲麻呂は帰国することができずに、中国に残って玄宗皇帝に重用され、正三品まで出世しています。
唐の玄宗皇帝の時代は古代中国の4大美人、楊貴妃の時代でもあり、西安市には玄宗皇帝や楊貴妃が使った豪華なお風呂が残されています。
楊貴妃は玄宗皇帝が寵愛しすぎたために国を傾かせた美女(傾国の美女)といわれるほどの伝説の美女です。
伝説の美女といえば、百人一首には小野小町が登場します。
花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに (小野小町)
恋に人生を費やした小野小町も時の流れには逆らえないことを悟ったものといえます。
古典落語から中国との文化交流まで思いを馳せることができる百人一首の世界を子ども達との「かるた」大会で楽しみたいと思います。
(事務所誌「ほなみ」第107号掲載)
弁護士 土屋 俊幸
著者:土屋 俊幸
![]()
パソコンのハードとOSに強く、当事務所のパソコン機器のメンテナンス係りです。自分で高性能のパソコンを自作しています。オーディオが趣味で、最近では、デジタル信号をアナログ信号に変換する機器(DAC)にiPadをつなぎ、どのUSBケーブルだと良い音ができるのかを試行錯誤をしています。ハイレゾ音源とYouTubeのヒアノ演奏や交響楽団の演奏を真空管アンプで、30年前に買ったスピーカーで、音の歪みのもたらす音に聴き入る時間をつくりたいと思っています。論文検索や技術情報の収集など情報検索を駆使しての情報集めを得意としています。オーディオの世界と仕事では燻銀の経験と粘りで頑張っています。