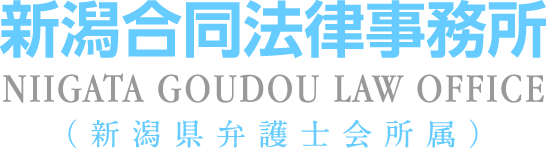2015年5月10日
緊急事態条項を憲法にくわえる?
連休明けの「憲法審査会」では、大規模災害を念頭においた「緊急事態条項」を憲法に加える方向で議論がなされています。
とくに、大規模災害が起きたとき、国政選挙を行えなくなる可能性に触れ、その必要性が強調されているとのことです。
この「緊急事態条項」(「国家緊急権」ともいいます)とは、非常事態の際に、憲法に決めてあるルールを一時停止し、そのときの内閣総理大臣に強いリーダーシップを認めようというものです。
公表されている自民党憲法草案では、①内閣が法律と同じ効力をもつ「政令」を制定できること、②財政支出を可能とすること、③自治体に命令ができることなどが挙げられています。
さて、災害時に「緊急事態条項」は、本当に必要なのでしょうか。
まず、第1に、大規模災害の際に、必要な法律は既に十分にあります。
これまでの政府は大規模災害時の対応(阪神・淡路、中越、中越沖、東日本大震災)の不備は、すでにある法律を十分に活用できなかった点と、事前の準備を行っていた点にあるものです。
決して、憲法に不備があったということはありません。(災害時に国会議員が不在?という点も参議院の緊急集会というものが用意されています)
第2に、そもそも憲法は市民一人ひとりの生命や財産や権利を守るために、政府に義務を負わせ、人権を保障するものです(これを「立憲主義」といいます)。
つまり、災害などで市民の人権が脅かされているときにこそ、まさに憲法の出番なのですが、これを停止することは、被災者中心の復興の妨げになるものと言えます。
第3に、この緊急事態条項(国家緊急権)は、「災害時」に、政府に強大な権力を認めるものです。
ですので、その性質上①非常事態を宣言しがち、②延長しがち、③濫用しがち、といった極めて危険性の高いものです。
このことは、「緊急事態」を名目に、独裁政権が成立したという歴史をみても明らかです(ワイマール憲法下におけるナチスドイツの例)。
「災害時の備えだというのだからなんとなくいいことなのでは?」というものではなく、
「緊急事態条項」は、不要かつ有害であり、極めて危険なものなのです。
これまで、災害復興支援にかかわってきた弁護士としては、大規模災害が起こったとしても「国家緊急権」は必要なく、
むしろ有害かつ危険なものでありその創設には強く反対します。
弁護士 二宮 淳悟
著者:二宮 淳悟
![]()
2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長 ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長