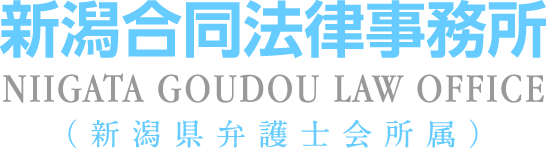2015年4月11日
子どもの加害行為と親の監督責任
昨日付の平成27年4月9日最高裁判決に関する齋藤裕弁護士の記事にフォローする形で投稿します。
子どもの加害行為によりその親に対して損害賠償を求めようとする場合、その法律構成としては、民法714条の責任無能力者の監督義務の責任を問う方法と、民法709条の一般不法行為責任を問う方法の2種類があります。
加害行為をおこなった子どもが責任無能力者である場合(一般には小学校高学年程度以下)、民法714条が適用され、親は原則として責任を負い、親が監督義務を怠らなかったことを証明しない限り、責任を免れることができないとされています。そしてこれまで、親が監督義務を尽くしたとして免責されるのは例外的な場合として取り扱われてきました。今回の最高裁判決は、一般的に危険とはいえないサッカー遊びを行っていたにすぎない場合について、親が監督義務を怠ったとはいえないと判断し、親の免責を認めた点で注目されるものです。
一方、子どもが責任能力を有する年齢に達している場合には(一般的には小学校高学年以上程度)、714条の適用はなく、709条によることになり、親に対して損害賠償を求めるためには、被害者側が親が親権者としての負っている一般的な監督義務に違反した事実を主張し、立証する必要があります。ただし、これまでの裁判例の中でも、責任能力がある子の加害行為であっても、709条を適用して、親に監督義務違反の損害賠償を認めた裁判例は多数あります。
今回の判例は、子に責任能力があるかないかによって、結論にドラスティックな差が生ずることを避けようとするものであるといえます。当該行為自体の危険性や子の年齢とそれに対応する監督義務のあり方(責任能力がないとされる子であっても11歳くらいの子と4~5歳の子、責任能力がある子であっても12歳の子と19歳の子では親の監督義務のあり方が異なって当然です。)を実質的に判断する姿勢を示したものということができそうです。
したがって、同様の事例に遭遇した場合、被害者側は安易に親に対する責任追及が認められないとあきらめる必要はなく、加害者側も責任がないと安心してしまうことは危険です。具体的な事案については、専門家である弁護士に相談して意見を求めることが大事であると思います。
お気軽にご相談ください。
新潟合同法律事務所 ℡025(245)0123
弁護士 近藤 明彦
著者:近藤 明彦
![]()
話しやすい雰囲気で相談・打合せを行い、丁寧な事件処理をすること。依頼者の皆様の満足と納得を最優先にし、安心感を得ていただけることを目標として頑張っています。以前依頼者であった方から、別の事件の相談を再び受けること(リピート)、別の相談者を紹介していただくこと(孫事件とでも言いましょうか)が多く、そのことが私にとって大きな励みになっています。お客様から満足していただけたかどうかのバロメーターであると考えるからです。
意外と知られていない自転車ルール その2
新潟県が水俣病特措法の異議を認める救済決定